どうでもいい話題も、図にすればなぜか深く見えてくる。
この番組は頭の体操、時々悪ノリ。見えるようで見えない構造をスッキリ整理する、そんな図解系ラジオです。
今回のテーマは「リクライブ8人中5人がコロナに。どうしようを図解」です。
「要件定義している時間がない」。災害現場や制作現場の非常時では、それが現実です。
3回にわたるポッドキャストでは、突発的な大量欠勤をきっかけに、山本純平さんが“要件推理”という独自の思考法で状況を整理し、業務フローの可視化からAIによるタスク再分配のプロトタイプまで、一気通貫で形にしていきました。この記事では、その“最短距離で動く方法”を具体例とともにご紹介します。
※ 本記事はポッドキャストの内容を元に生成AIを活用して記事化・図解しています。
要件定義ではない、要件推理とは?

要件推理とは、一言でいえば「聞く前に考える要件定義」です。
普通のプロジェクトでは、ヒアリングして、まとめて、承認をもらって…という順番で進みますが、現場が混乱しているときにそんな時間はありません。
山本がやるのは、話を全部聞き終わる前に「自分が現場責任者ならこう組む」という仮説を先に出すこと。
相手に“叩いてもらう”前提で、最初のたたき台をスピード重視で見せる。すると「あ、それ違う」「いや、こっちはOK」と、要件が一気に具体化していくんです。
目的は“正確さ”ではなく“動かすこと”。100点の仕様書をつくるより、70点でも現場が回る仕組みを先に出す。
それが要件推理の真骨頂です。
5人同時欠勤。どう動く?
ある週、リクライブで8人チームのうち6人が体調不良。
「これはマジでやばい」となった瞬間、最初にやったのは“仮説で動く”ことでした。
課題はざっくり3つ。
①欠勤を予測できない
②休んでも回る仕組みがない
③外部パートナーをうまく活かせてない
理想の絵はこうです。
スマートリングなどで体調の兆候をキャッチ → タスクをクラウドで一元管理 → AIが自動で仕事を再分配 → それでも足りない分は外部パートナーにSOS。
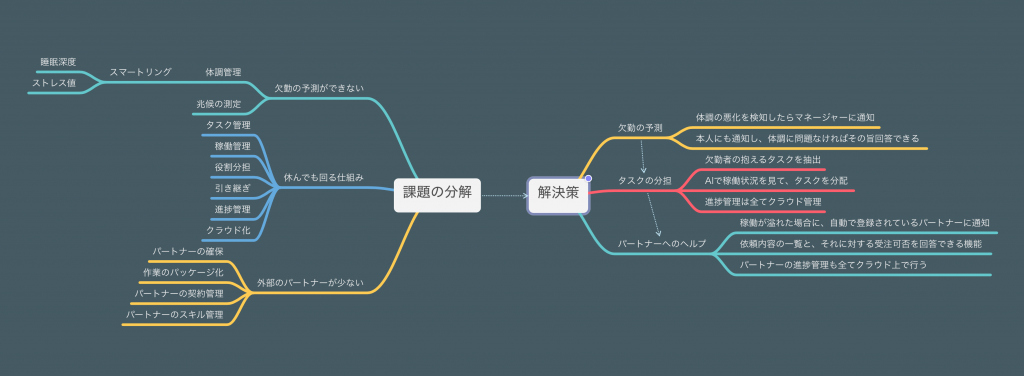
細かいルールは後でいい。まずは「この流れでいけそうか?」を関係者に見せる。
完璧よりスピード。これが、非常時の現場を前に進めるコツです。
“読める”業務フローを描く――平時と有事の二層設計
次にやったのは業務フローの整理。
誰が、いつ、どのシステムで、何をするのか。
これを“見てわかる”レベルに落とし込みます。A3で読めない図はNG。
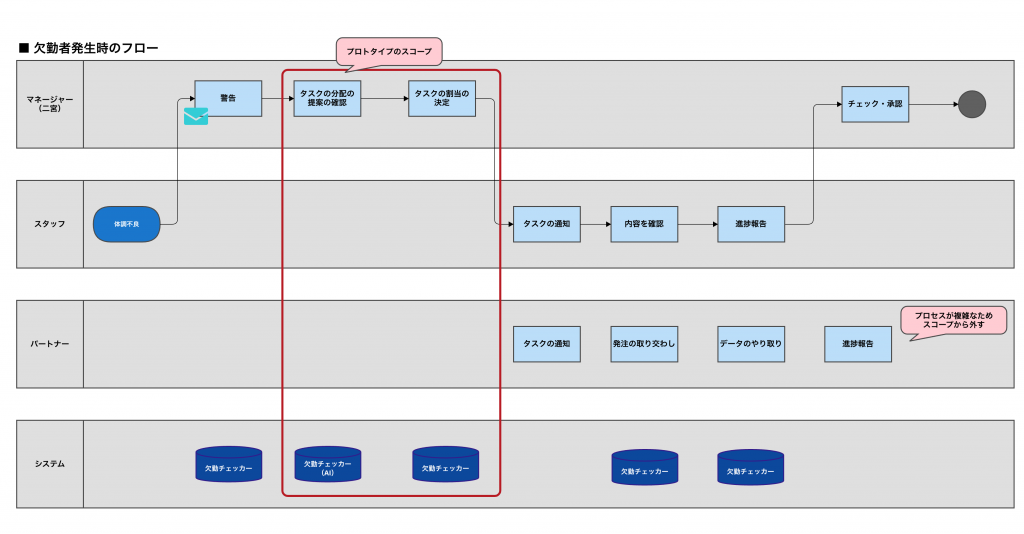
レーンは4本。〈マネージャ/スタッフ/パートナー/システム〉。
平時フローは「依頼→登録→アサイン→進捗→レビュー→完了」。
有事フローは「体調アラート→影響タスク抽出→AI分配→承認→外注→完了」。
大事なのは“正しい図”じゃなく、“全員が同じ絵を見て話せる図”にすること。
議論の土台ができれば、次のプロトタイプづくりが一気に速くなります。
業務フローは“正解を描くもの”ではなく、“会話を生むもの”です。
全員が同じ図を見て議論できることが、次章で紹介するプロトタイプの精度を上げる鍵になります。
AIでタスクを再分配してみた
ここからは実験フェーズ。
題材にしたのは「ポッドキャスト編集タスク」。公開日が固定されていて、属人性も比較的低い。ちょうどいい。
必要なデータはシンプルです。
件名・概要・担当者・優先度・カテゴリ・公開日・想定工数・リンク。
これだけあればOK。
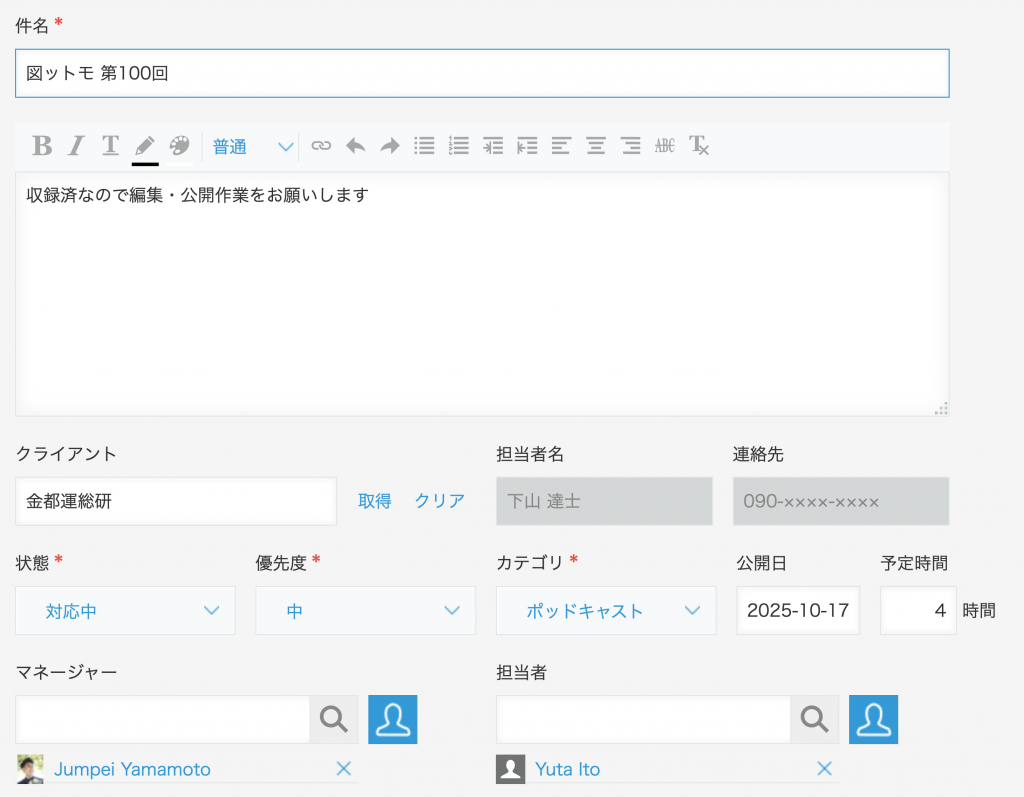
欠勤した人の“公開日直前タスク”をAIが自動抽出。
ほかのメンバーの工数・締切と照らし合わせて再分配案を出します。
マネージャーが「承認」ボタンを押せばタスクが更新され、負荷はきれいに平準化。
“明日の混乱”を前日に防げるようになりました。
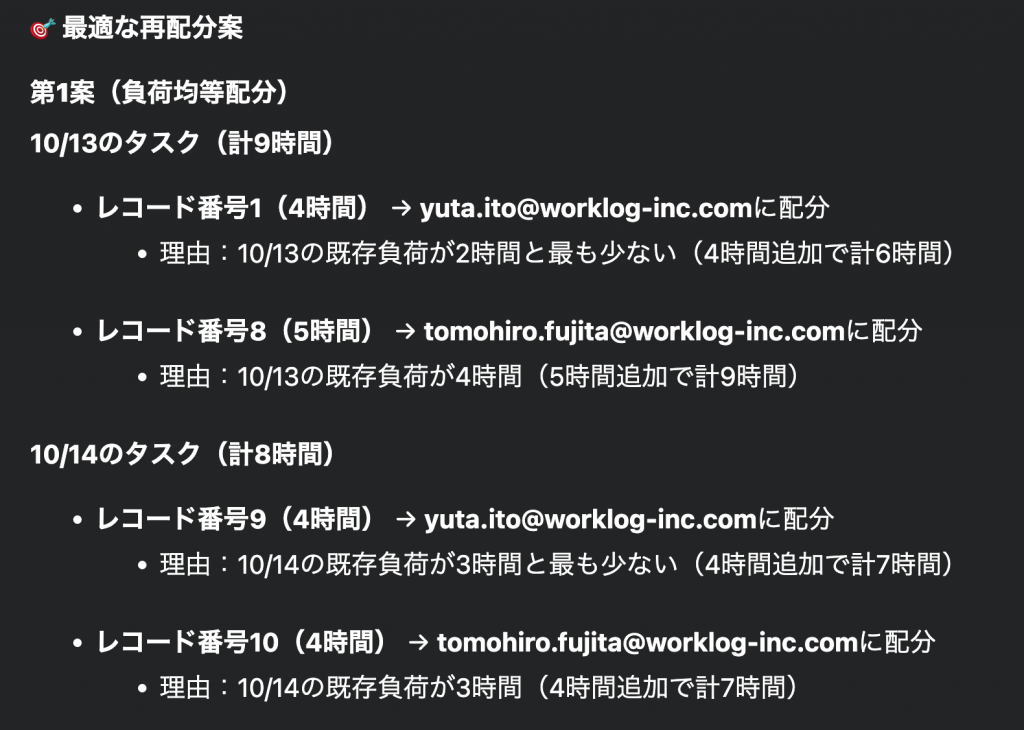
さらに、スキルタグや機材制約を入れれば、より現実的な分配も可能です。
全部を自動化しようとせず、“効くところから動かす”のがポイントです。
今後はスキルタグ(編集/デザイン/収録など)や機材・リモート可否を属性として追加することで、より精緻な分配が可能になります。
重要なのは「全部を自動化しない」こと。属人性の低い領域から段階的に始めることで、最小労力で最大の効果を得られます。
現実との折り合いをつける
理想はかっこいい。でも現実は、予算と契約の壁があります。
だから、最初から100点を狙わず、できるところから。
- 体調予測は“あればいい”。まずは欠勤申告フォームで代用。
- 外注は“常時プール制”。スキルカードと単価、NDAのテンプレを先に準備。
- 見積りは“段階課金”。「フロー設計 → プロトタイプ → 拡張」で区切る。
運用の工夫も大事です。
公開日×工数で赤信号を出し、AI提案→承認→通知→更新をワンクリックにまとめる。
人は「判断」に集中し、システムが「動作」を担う——そんな分担が理想です。
まとめ――非常時を“ふつう”にする
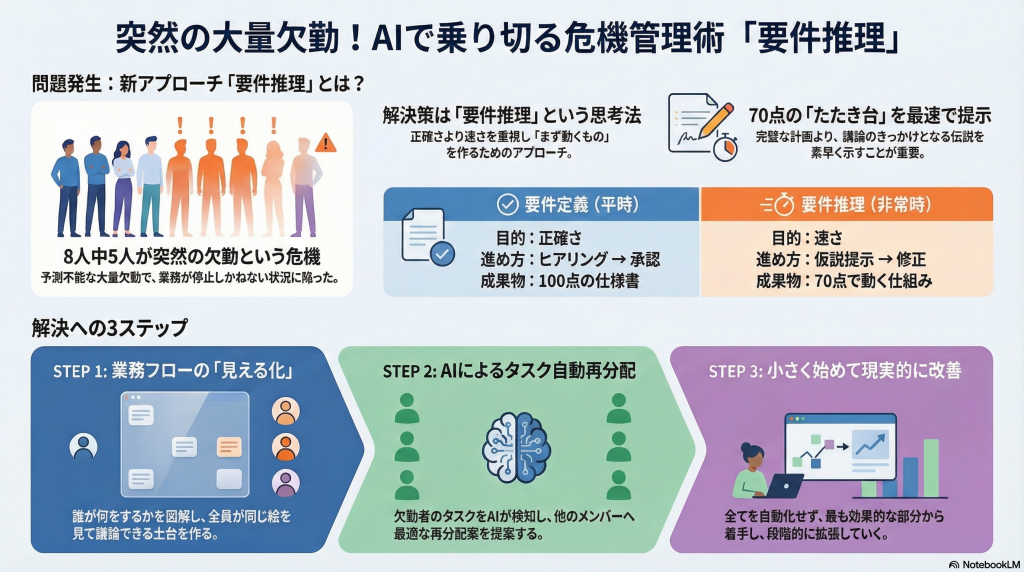
要件定義は“正確さ”の技術。
要件推理は“速さ”の技術です。
非常時には、まず“動くもの”をつくって、そこから叩いてもらう。
A3で読めるフローと、最小限のデータ定義、AIの自動分配。
この3つがそろえば、「誰かが休んでも回るチーム」は現実になります。
完璧を目指さず、まずは一歩。
公開日が動かない仕事から始めて、小さく効かせていく。
それが、非常時を“ふつう”に変える最短ルートです。


